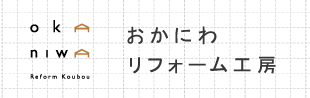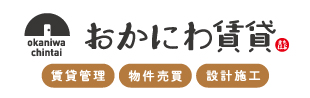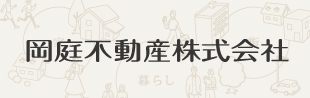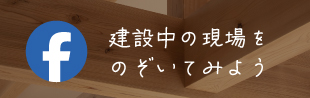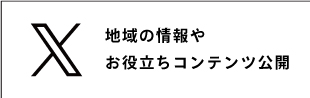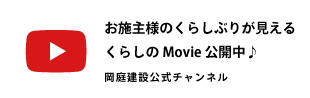スタッフブログBLOG
お役立ち情報(42件)
記事一覧へ
いよいよ始まる新NISA その7
さて、投資信託ですが、利益を確約するものではありません。 戦争や災害、経済問題、マイナスの材料はたくさんあります。 ですが、投資信託の運用実績は、過去22年間で年3.59%プラスです。 これだけではイメージできないでしょうから具体的に。 毎月3万円を20年間積み立てたとします。 20年後、まったく運用しなければ720万円になります。 仮に年3%で運用出来たら、20年後981万円になり、261万もプラスです。もし年5%で運用出来たら、20年後1217万円になり、約500万もプラスになります。 今、定期積金の利率は0.002%です。これで20年積み立てたとしたら、20年後どうなると思いますか?なんと,7,201,434円 利息は1,434円しか付かないうえに、税金も取られます。 何度も言いますが、投資信託の利益は確約できません。でも、ただ単に銀行に預けるのは、得策ではないような気がします。 豊村岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。 その1、その2、その3、その4、その5、その6、その7、その8、その9、その10、その11
2023.10.13(金)

いよいよ始まる新NISA その6
投資信託とは?信託は信じて託することです。投資を誰かに信じて託すのが、投資信託です。 では誰に託すのでしょうか?資産運用の専門家である運用会社に託します。 自分の手元に1万円があり、これを投資するとします。でも、今の日本の平均株価は3万3千円ぐらいですが、1万円では買えませんね。日本の国債も最低5万円ですので、1万円では買えません。 そこで、投資信託です。自分の1万円、同じような人が1万人いたら、1億円になります。この1億円を運用会社が、複数の商品(株式や債券、不動産)に分散して投資することによって、利益を得ます。 自分はお金を出して、そのほかは運用会社にお任せ、それが投資信託です。 豊村 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。 その1、その2、その3、その4、その5、その6、その7、その8、その9、その10、その11
2023.10.06(金)

いよいよ始まる新NISA その5
そもそも、投資とはなんでしょう? 投資の意味は、利益を見込んで自己資金を投じることとなっています。 最初の方に例を挙げた株取引も投資で、売買による利益と配当による利益があると書きました。売買をして得た収益を「キャピタルゲイン」、配当など保有していて得る利益を「インカムゲイン」といいます。 株取引のほかに、債券、投資信託、外貨預金、FX、仮想通貨、ETF(上場投資信託)、不動産投資、金、先物取引等々があります。 債券とは要は借金です。国が発行していれば「国債」、会社が発行すれば「社債」です。借金ですから償還期限に返済を受け、利息が付きますので、それが利益です。それと、ややこしいのですが、債券自体にも時価というものがあり、100万円の国債が110万で売られたり、90万で売られたりがあり、キャピタルゲインも存在します。 さらに、国内の株式、外国株式、内国債券、外国債券と種類があります。 もう種類が多すぎて、ギブアップしそうです。 そういう人のために、NISAで使われる投資信託というものがあります。 豊村岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。 その1、その2、その3、その4、その5、その6、その7、その8、その9、その10、その11
2023.09.29(金)

いよいよ始まる新NISA その4
2024年から始まる新NISA 変わるのは次の点です ①恒久化 区切られていた期間がなくなり、恒久的なものとなります。 ②無期限化 一般NISA:5年、つみたてNISA:20年だった期限がなくなり、無期限になります。 ③年間投資額360万円 一般NISA:120万円、つみたてNISA:40万円だった投資限度額が、合わせて360万円になります。うち120万円は今までのつみたてNISAと同様の積立投資に使えます。加えて240万円が成長投資枠として、積立投資のほか個別株式や投資信託に使うことができます。 ④投資上限1800万円(うち成長投資枠1200万円) 残高ベースで1800万円(うち成長投資枠1200万円)が上限となります。残高ベースとは、買った累積の金額ではなく、売ることもして、残高が1800万円以内ということです。 ⑤残高の簿価管理 残高は取得価格(簿価)で管理されます。つまり100万円で買ったものが150万円で売れたとしても、残高は100万円減ったことになります。 ⑥旧NISAとの併用可 すでにNISAを利用している場合、新NISAとは別枠で併用可能です。 以上が新NISAの特徴になります。 豊村岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています その1、その2、その3、その4、その5、その6、その7、その8、その9、その10、その11
2023.09.22(金)
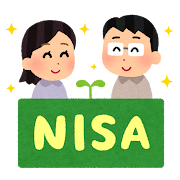
いよいよ始まる新NISA その3
投資額に年間限度額を設けて、投資益を非課税とするNISAですが、期間が決まっていました。 他方iDeCoというものがあります。個人型確定拠出年金というもので、毎年iDeCo商品を買うものです。毎年毎年買う=積立るわけですが、その積立金額を60歳以降受け取ります。iDeCo商品はNISAと違って、個別株式への投資はないですが、投資信託や預金などをが対象となり、運用益は非課税となります。受け取るときも退職金や公的年金と受け取ることができます。ただし、60歳になる前にやめてしまうと、非課税とかの恩恵はなくなります。 2018年つみたてNISAが始まります。これは、投資信託のみが対象ですが、年間40万円を限度として、積立で投資を行い、20年間運用益は非課税というものです。iDeCoと違って、投資商品の売却はいつでもできて、売却益も非課税です。これも2023年で終了となります。 今あるNISAはどれも2023年で終了するわけですが、2024年からは新NISAが始まります。 豊村 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています その1、その2、その3、その4、その5、その6、その7、その8、その9、その10、その11
2023.09.15(金)

いよいよ始まる新NISA その2
投資というと、まず株取引が浮かぶかもしれません。 株取引には二つあります。まずは、売買です。 株には株価という値段がついてるわけです。10万円で買ったものが15万円で売れれば、5万円の利益。逆に8万円で売ったら2万円の損。 もう一つは、配当です。 株式を発行している会社は株を買ってもらい=資金を出してもらい、その代わり利益を株主に分配(配当)をします。 売買の利益にも配当にも所得税が課税されます。 2014年に年間100万円を限度として、この売買益や配当益を非課税とする制度が始まりました。これが最初の一般NISAです。株式だけではなく投資信託などが対象です。非課税の期間は5年間、その後年間120万円まで限度額が増額して、今年2023年までで終了となります。 2016年には子供や孫が18歳になるまで年間80万円を限度額とするジュニアNISAもスタートしましたが、今年2023年で終了です。 ちょっと長くなるので続きます。 豊村 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています その1、その2、その3、その4、その5、その6、その7、その8、その9、その10、その11
2023.09.08(金)

いよいよ始まる新NISA その1
2024年から、新NISA制度が始まります。 NISAについては何度か書いていますが、2024年から新制度が始まりますので、改めて書いていこう思います。 なぜ、いまNISAやiDeCo等の投資が話題になっているのでしょうか? 不況、物価上昇、円安等が続いている中、株価はじわじわ上がっています。平均所得もここ30年変化なしです。 平均寿命も上がり、老後といわれる期間がどんどん長くなっています。 公的年金だけで安定した生活する事が、正直不安です。 となると、自分で何とかすることを考えていかないといけません。 そのうちの一つが投資です。 NISAやiDeCoはその投資の方法なわけですが、色々優遇措置があるので、利用したほうが得ではないかと思えます。 当然リスクもありますので、盲目的におすすめというわけではないのですが、しばらくお付き合いください。 豊村 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています その1、その2、その3、その4、その5、その6、その7、その8、その9、その10、その11
2023.09.01(金)

タワマン節税の終わり その6
2024年から変わるタワマン節税ですが、どのように変わるのか? 今まで書いてきたように、相続税における評価額が、市場価格とくらべると著しく低くなる。 これが、節税のポイントです。 ここにメスが入り、評価額は市場価格の6割を限度とすることになります。 前述の計算でいうと ≫死亡時に借金がまだ8000万円残っていて、マンションの市場価格が9000万円であり、他に財産が3000万円あったとします 市場価格の6割ですから、9000万×0.6=5400万円 5400万+3000万‐8000万=400万に相続税が課されることになります。 これが始まるのが、2024年1月からですので、今タワマンを持ってる人は、年内に贈与したほうが良いかもしれないですね。 でも、良くも悪くもこの節税ができたから、タワマンを買った人もいるわけで、そういう人たちがいなくなったら、タワマンが売れなくなって、市場価格も下がるってことも考えられますね。景気にはよくないのでは? 豊村 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています その1、その2、その3、その4、その5、その6
2023.08.25(金)

タワマン節税の終わり その5
タワマン節税とは何か、おわかりいただけましたでしょうか? 首都圏にタワーマンションがいっぱい建っていて、すぐに売れちゃって、お金持ちがたくさんいるんだなって思ってました。 でも、この節税方法を使って、借金をして何部屋もタワマンを購入して、人に貸して家賃を借入金の返済に充てる人も結構いるわけです。 借金をするには普通担保と返す当てがあるかどうかが必要です。タワマンなら、市場価値がそれほど下がらないので、担保価値が充分にあり、家賃で返済できるので、条件は備わっています。 これは、相続だけではなく贈与についても同じことが言えます。持ってるタワマンを親族に贈与するときに、借金も一緒に贈与する負担付贈与という方法をとれば、贈与税の負担が軽減されます。ただし贈与した親の方に、所得税がかかる場合もあるので、注意が必要です。 そんなタワマン節税、いつまでも国が放置しているわけもなく、2024年からは状況が変わります。 続きます 豊村 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています その1、その2、その3、その4、その5、その6
2023.08.18(金)

タワマン節税の終わり その4
さて、前振りが長かったですが、タワマン節税とは何かです。 自宅としてだけではなく、賃貸用にタワーマンションを購入した場合。仮に1億円の借金で、1億円の物件を購入したとします。購入後何年か経って、購入した人が亡くなり、相続税の計算をすることになります。死亡時に借金がまだ8000万円残っていて、マンションの市場価格が9000万円であり、他に財産が3000万円あったとします。 とすると マンション9000万+財産3000万‐借金8000万=4000万に相続税が課せられそうですが、違います。 前述の通り、相続の時にマンションは市場価格ではなく評価額で計算します。仮に市場価格の半分とすれば、4500万ぐらいになります。 とすると、マンション4500万+財産3000万‐借金8000万<0円 となり、相続税はかからないことになるわけです。 借金8000万はマンションの借金だから、その分しか引けないんじゃないのと思うかもしれません。でも、借金はマイナスの財産として、プラスの財産から全額引くことができるわけです。 これがタワマン節税です。 続きます。 豊村 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています その1、その2、その3、その4、その5、その6
2023.08.04(金)